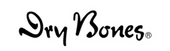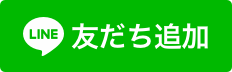New & Restock
All products
-
Step Ribbon Braid Hat “SMALL PATTERN”
通常価格 ¥28,600 JPY通常価格単価 あたり -
Hand Stitch Open Shirt
通常価格 ¥20,900 JPY通常価格単価 あたり -
L/S Open Shirt “Chambray Dobby”
通常価格 ¥28,600 JPY通常価格単価 あたり -
Dobby Open Shirt “LOZENGE”
通常価格 ¥28,600 JPY通常価格単価 あたり -
S/S Hawaiian Shirt “BEER”
通常価格 ¥26,950 JPY通常価格単価 あたり -
L/S Hawaiian Shirt “BEER”
通常価格 ¥26,950 JPY通常価格単価 あたり -
Cotton Sweater “BLACK PANTHER”
通常価格 ¥19,910 JPY通常価格単価 あたり
Shop List

Brand
Dry Bones
Dry Bones(ドライボーンズ)とは
「懐古趣味紳士用品店」として、
1920~70年代の
ヴィンテージクロージングを基に
独自のデザインを加えた、
温故知新な物作りを展開している
メンズブランドです。